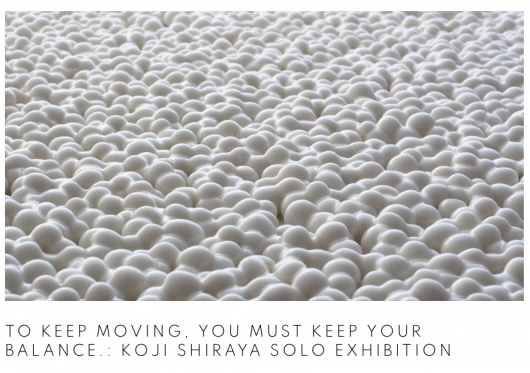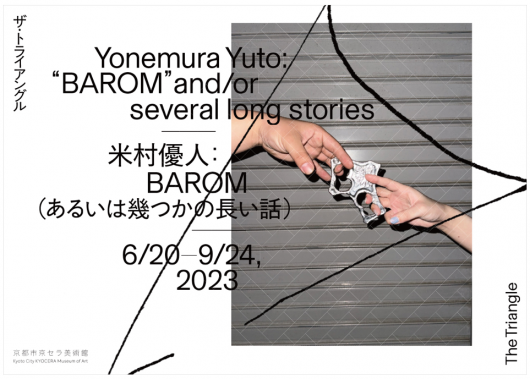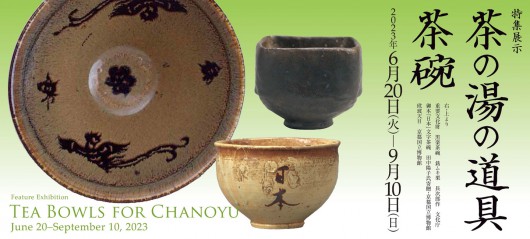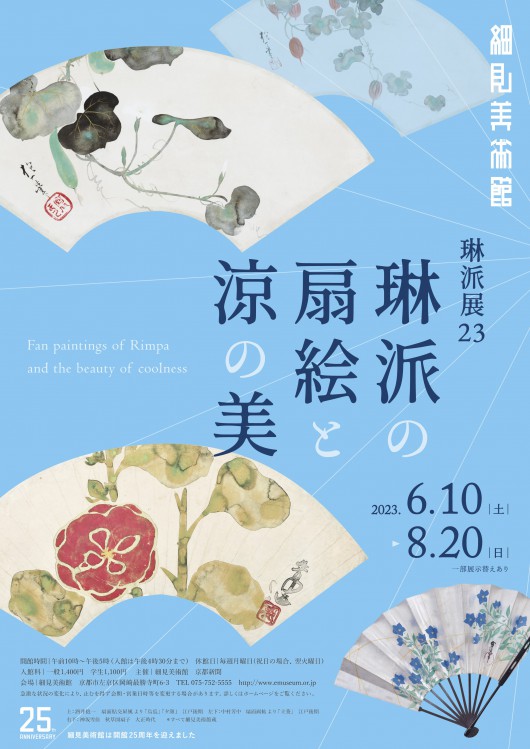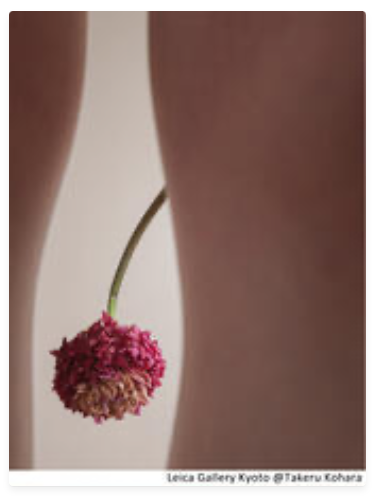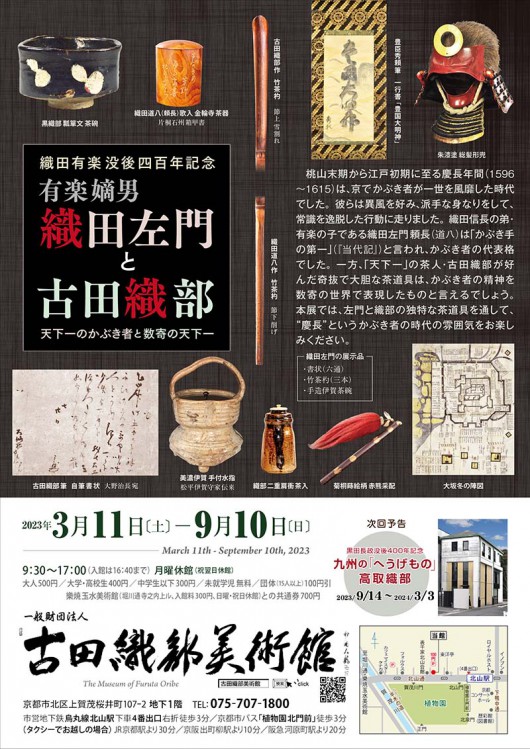HAPSスタジオ使用アーティストの三枝愛(禹歩)が、
「いきいき楽ちゃんフェスティバル 楽し夏祭り」に「紙屋川コーナー」のブースを設けます。

概要
いきいき楽ちゃんフェスティバル 楽し夏祭り
日時:2023年8月12日(土)17:00~21:00 ※小雨決行、雨天の場合は多目的ホールにて実施
会場:楽只保育所 園庭(京都市北区紫野西舟岡町2)
三枝愛(禹歩)は、紙屋川(現在の天神川)でかつてつくられていた和紙のリサーチを「紙屋川を漉き返す」と題して行っています。現在は11月に紙屋川で紙漉きを行うことを目標に、楽只児童館の子どもたちと和紙の原材料となるトロロアオイの栽培を進めています。
今回、元楽只(らくし)小学校跡地の楽只保育所園庭で開催される「いきいき楽ちゃんフェスティバル 楽し夏祭り」に「紙屋川コーナー」のブースを設け、紙屋川だよりの号外配布と、トロロアオイの葉をモチーフとした手ぬぐいの販売を行います。手ぬぐいの売り上げは「紙屋川を漉き返す」の活動資金として活用いたします。みなさまのご来場をお待ちしております。
アーティストプロフィール
三枝愛(みえだ あい)
アーティスト。1991年埼玉県生まれ。京都を拠点に活動。2018年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。近年の主な活動に、2022年「ARTS CHALLENGE 2022」(愛知芸術文化センター/愛知)同展では沢山遼賞、竹村京賞をダブル受賞。2021年「ab-sence/ac-ceptance 不在の観測」(岐阜県美術館/岐阜)、「A Step Away From Them 一歩離れて」(ギャラリー無量/富山)、個展「尺寸の地」(Bambinart Gallery/東京)、「沈黙のカテゴリー | Silent Category」(Creative Center OSAKA/大阪)など。
禹歩(u-ho)
島貫泰介(美術ライター/編集者)、三枝愛(アーティスト)、捩子びじん(ダンサー・振付家)によるリサーチ・コレクティブ。ギリシャ悲劇『アンティゴネー』、大逆事件、葬送をテーマにリサーチを行い、そこから得た/派生した知見を作品化してきた。2021年度から京都市内のHAPSスタジオ使用者に採択され、活動を続けている。