
アートスペース浄土複合は2022年に、京都市左京区鹿ヶ谷にシェアスタジオをオープンしました。
大文字の麓で自然と歴史の感じられる閑静な地域にありながら、書店やギャラリー、ライブハウスといった文化施設の点在するエリアで、スタジオ利用者が制作を行なっています。
所在地|京都市左京区鹿ヶ谷法然院西町
空間|1区画 3×2.6m程度、シェアキッチン付き、計6区画
対象|ジャンルやキャリアは問いません。アートをはじめとする創作活動に携わる方。
利用料|月額25,000円(光熱費、運営費含む)
設備など|1区画 3×2.6m程度、シェアキッチン付き、計6区画
ウェブサイト|https://jodofukugoh.com/studio/


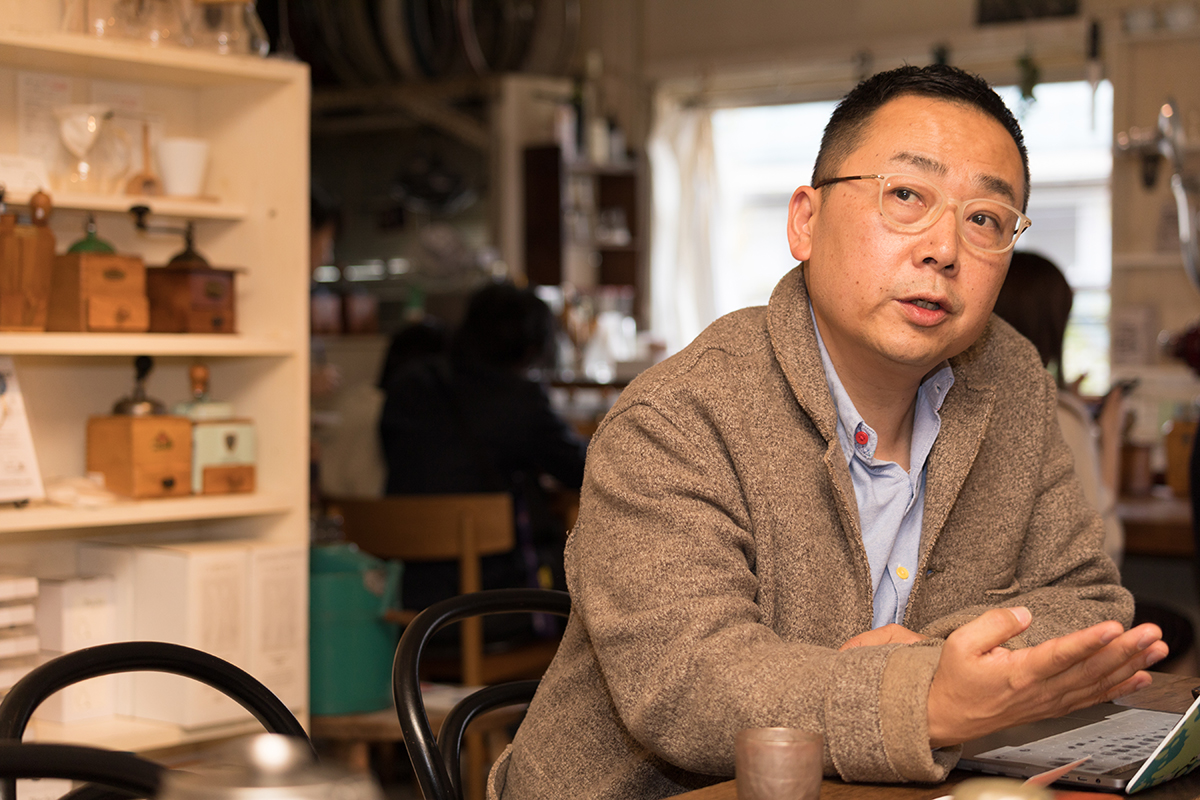

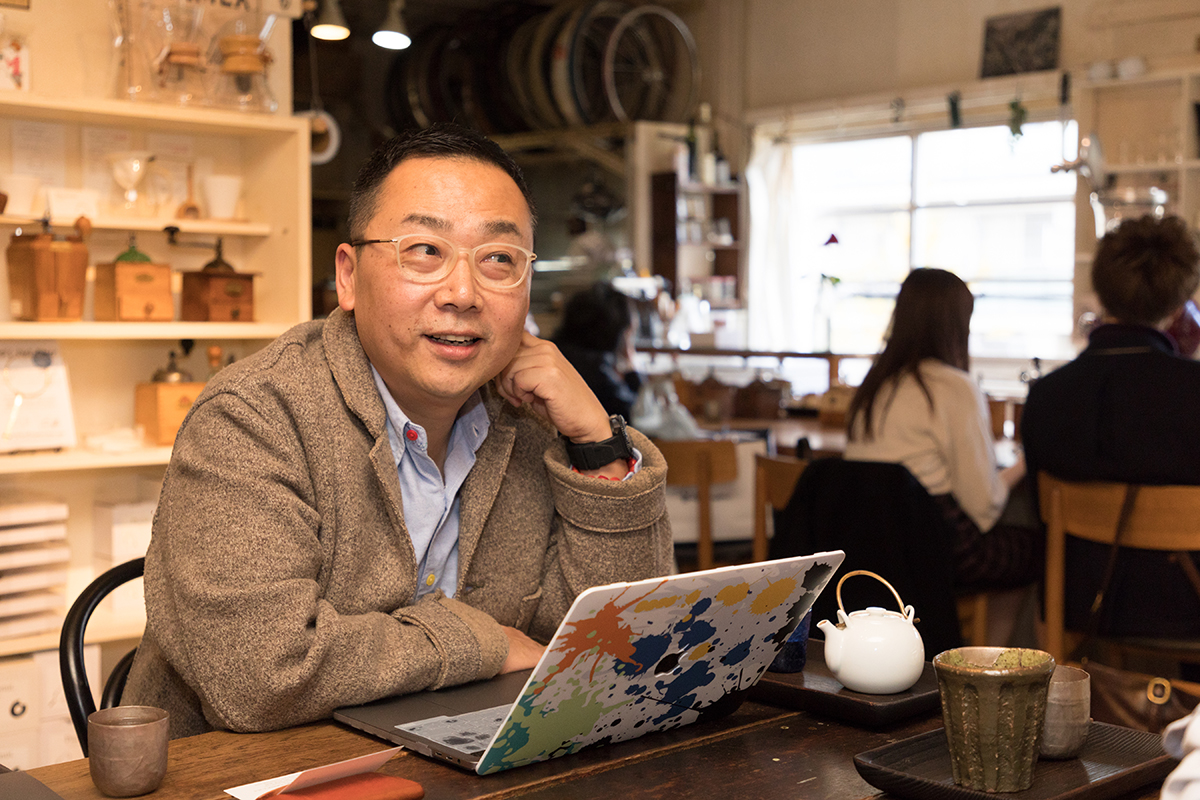







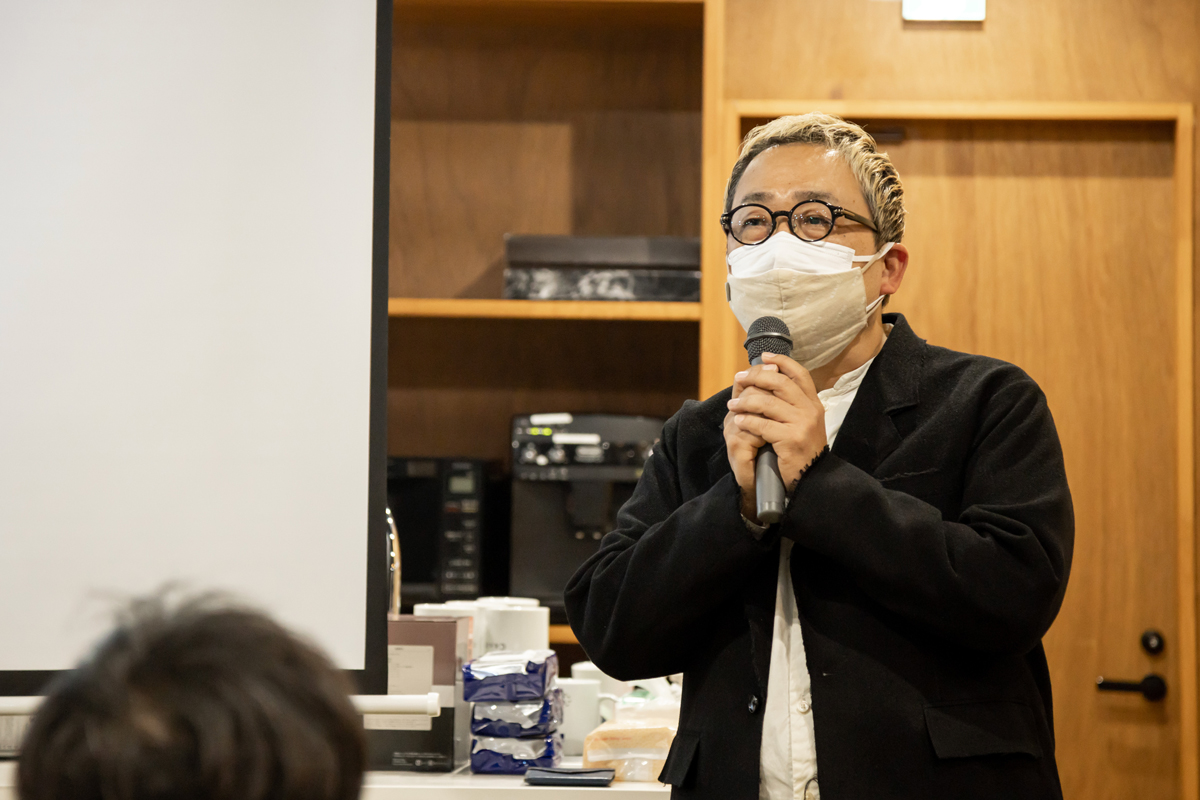












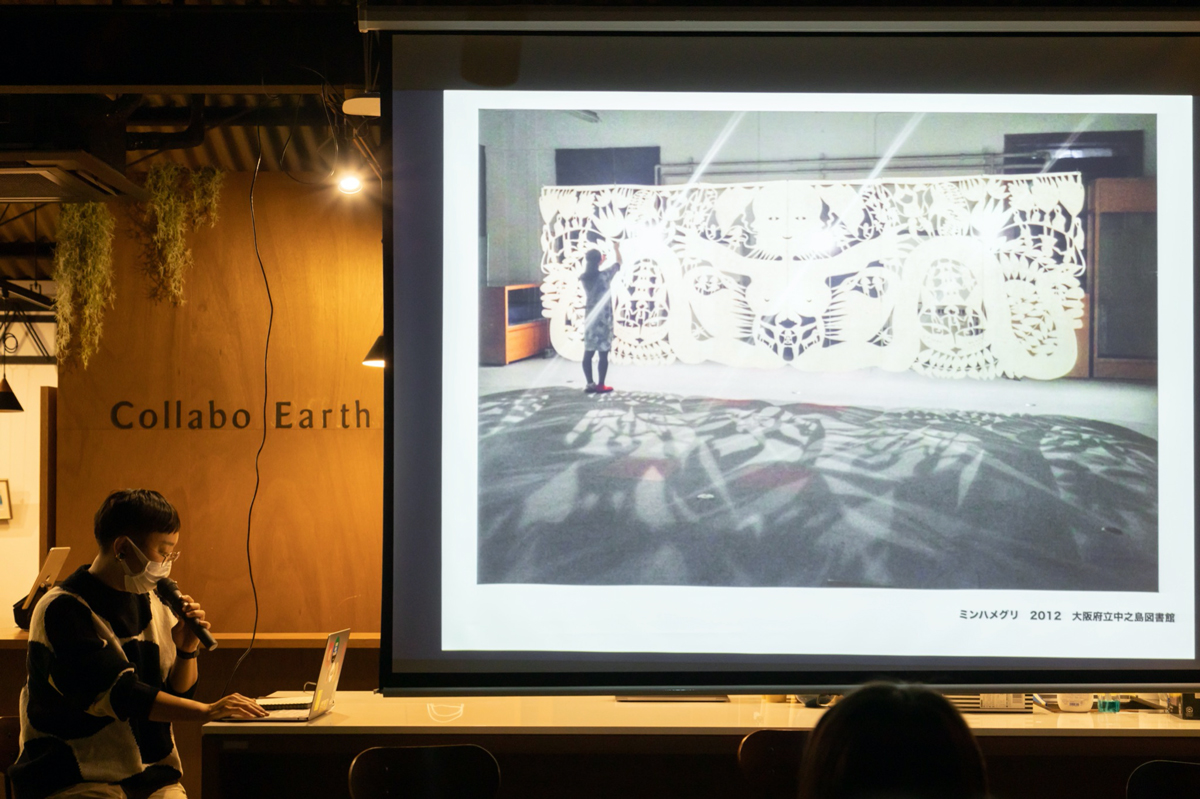


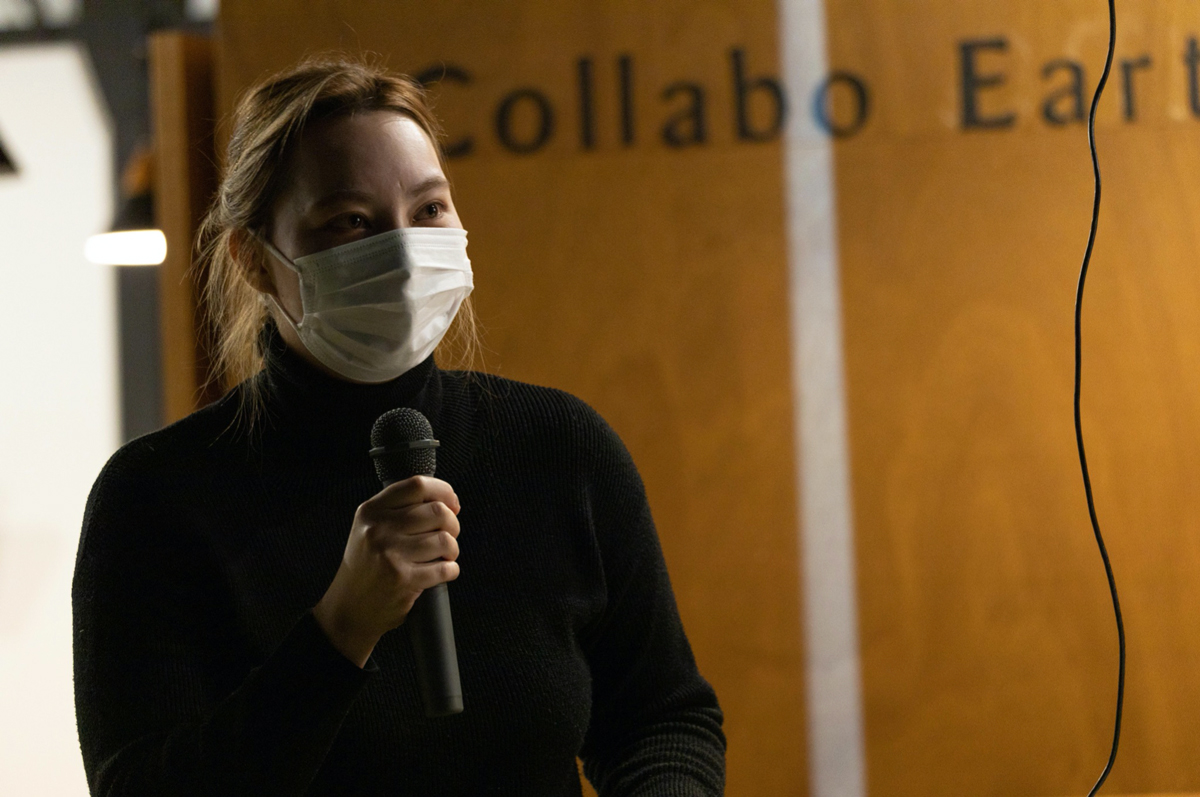







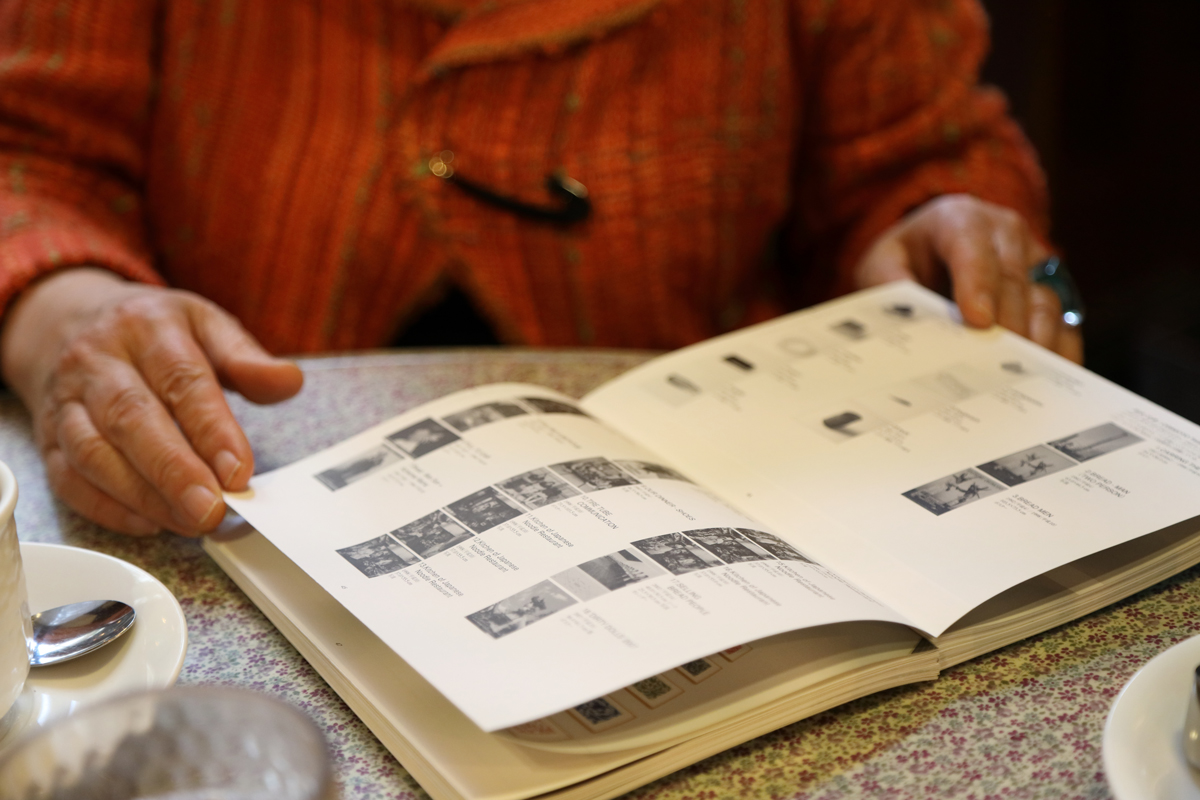


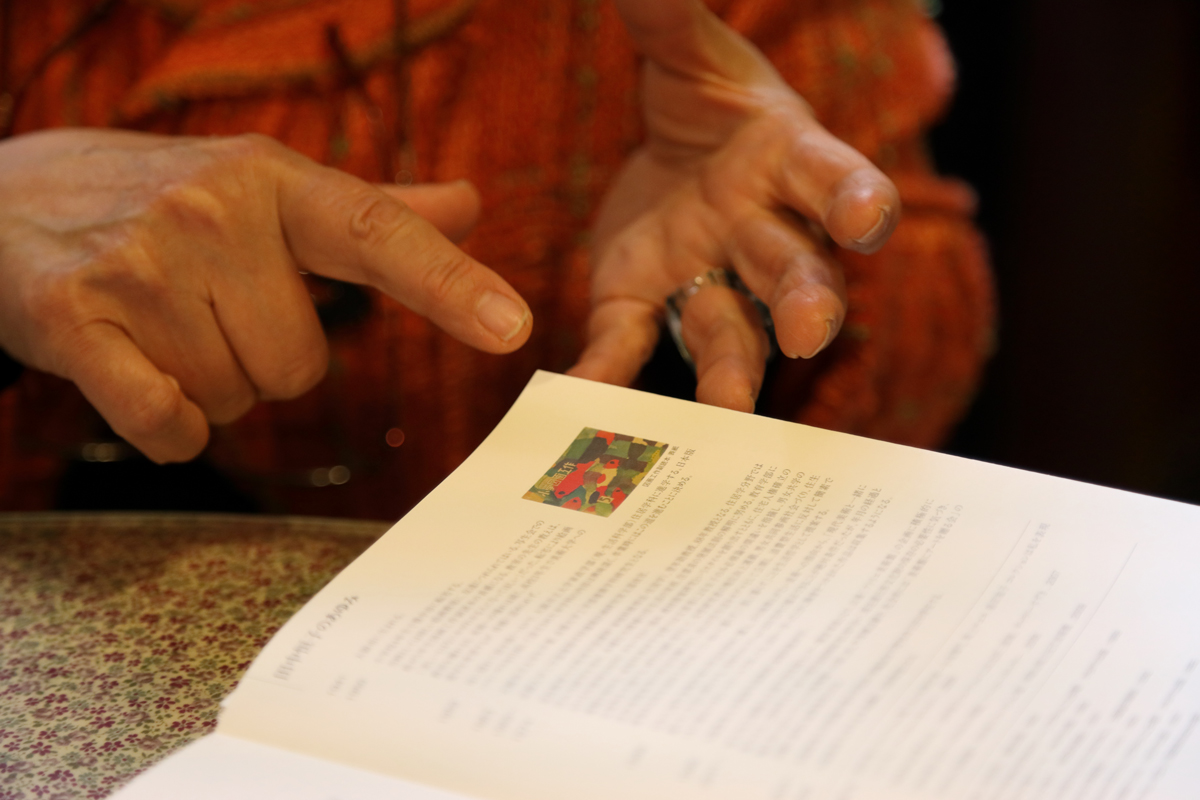





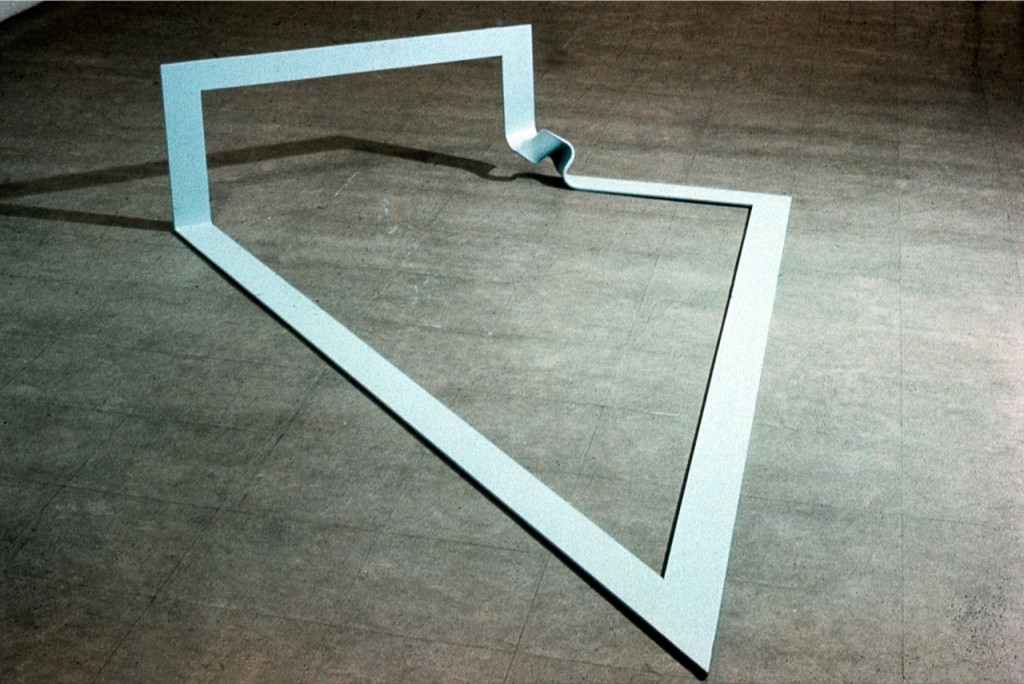


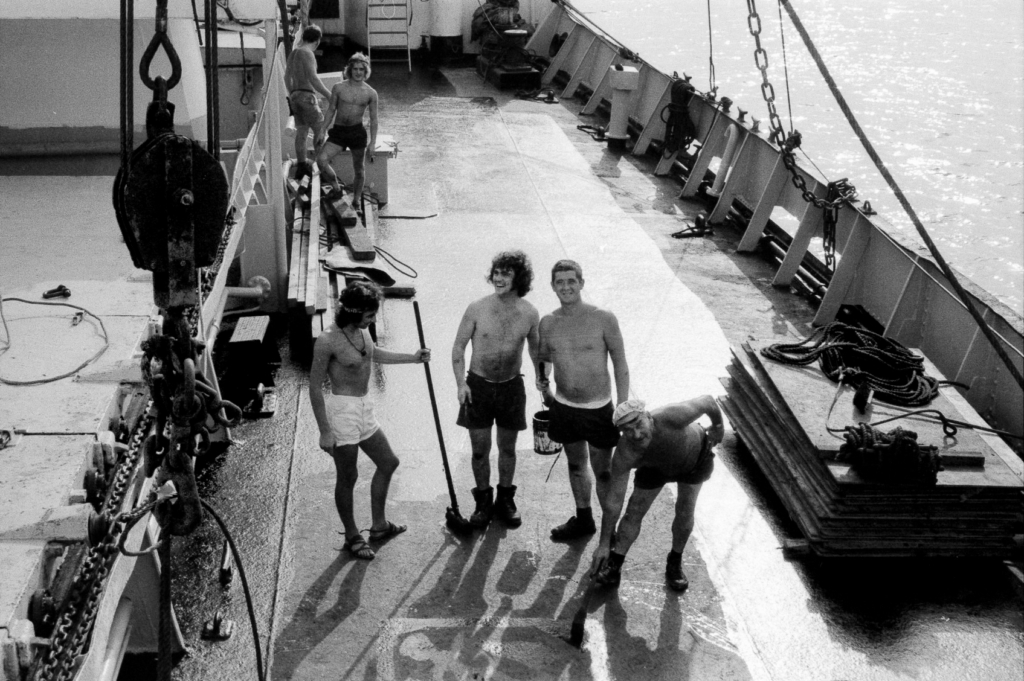








 初代実行委員は小原啓渡、高谷史郎(ダムタイプ)、松尾惠(ヴォイスギャラリー主宰)、木ノ下智恵子(当時、神戸アートビレッジセンター アートプロデューサー)らがチーム。
初代実行委員は小原啓渡、高谷史郎(ダムタイプ)、松尾惠(ヴォイスギャラリー主宰)、木ノ下智恵子(当時、神戸アートビレッジセンター アートプロデューサー)らがチーム。







